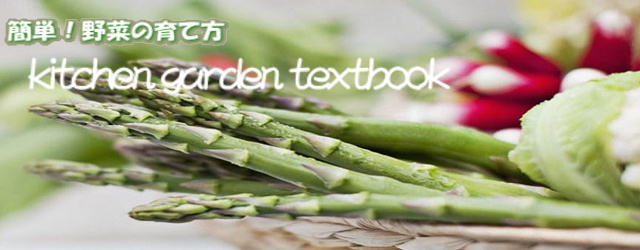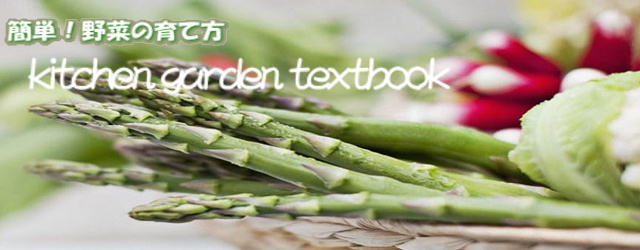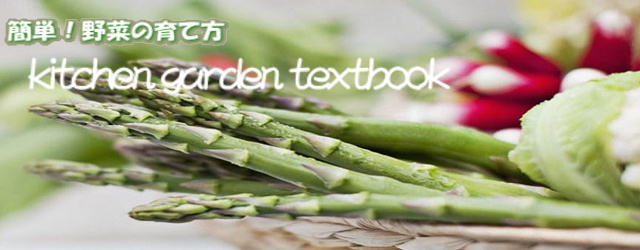 |
|
|
|

|
蕪(カブ)の上手な育て方!
|
 蕪(カブ)栽培 蕪(カブ)栽培
難易度★★☆☆☆
蕪(カブ)は冷涼な気候を好み暑さと乾燥に弱いので、春または秋に種を蒔いて育てましょう。茎葉の成長は温暖な気候が根の肥大には冷涼な気候が適しているので、初心者は秋蒔きが育てやすいです。
蕪はアブラナ科の根野菜で、原産地は地中海沿岸やアフガニスタンと言われています。日本には奈良時代に伝わり江戸時代に各地で改良されたこともあり、品種がとても豊富な野菜です。
蕪は害虫被害に遭いやすいので、害虫や病気に強い品種を選んだり寒冷紗などでプランターを覆って害虫の飛来を防いで育てるなど対策すれば大丈夫です。
カブに含まれる栄養価は、根にはビタミンC、カリウム、カルシウム、食物繊維など。アミラーゼという消化酵素を含むので内臓の働きを助け胃もたれや胸焼けに良いと言われています。
カブは葉も料理に使えます。葉には多くのビタミンやミネラルを豊富に含むので、味噌汁の具やお浸しにして美味しく食べましょう。 |
|
| |
| |
| |
| |
蕪の栽培カレンダー
|
春蒔きは3月~6月下旬、収穫は5月下旬~7月下旬
秋蒔きは8月中旬~10月上旬、収穫は10月中旬~12月中旬まで |
 |
|
| |
蕪を上手に育てるポイント!
|
- 蕪の生育適温は15~20℃、発芽適温は20℃~25℃。
- 冷涼な気候を好む蕪は春と秋が種まきシーズン。植える季節に合った品種を選ぶようにしましょう。
- 蕪は土壌への適応性が高くPH5.2~6.8と広いPHで栽培が可能です。
- 蕪は植え替えが出来ないので畑に直接種を蒔いて育てましょう。
- 有機質を含む保水性と通気性の高い砂壌土で良く育ちます。石や土の塊があると根割れや又根の原因になるので用土をよく耕して細かくしておきましょう。
- プランターや鉢で蕪を育てる時はミニ種がおすすめです。
- 種を蒔いてから発芽するまでの間は水切れを起こさないことが発芽率を上げるポイントです。
|
|
| |
蕪栽培に使うプランターと土づくり
|
 蕪を栽培する時に使うプランターサイズは、中型の標準タイプ(60㎝)以上で育てましょう。 蕪を栽培する時に使うプランターサイズは、中型の標準タイプ(60㎝)以上で育てましょう。
2条植えの時は幅が広い大型のプランターを利用します。大型の植木鉢なら少数株を栽培することが可能です。
 蕪栽培に使う用土は市販の培養土が便利で簡単です。自分で用土を作る時は 蕪栽培に使う用土は市販の培養土が便利で簡単です。自分で用土を作る時は
赤玉土6:砂2:バーミキュライト3、これに石灰を用土10ℓ当たり10gと化学肥料を用土10ℓ当たり20g混ぜ合わせた物を用土として使いましょう。種蒔きの2週間前までには土作りを完了させておきます。
蕪を露地栽培で栽培する時は、種蒔きの2週間前に石灰100g/㎡・堆肥2㎏/㎡・化成肥料100g/㎡を施して、畑をよく耕しましょう。畝は平畝で幅60㎝高さ10㎝にしましょう。水はけが悪い畑では20㎝の高畝にします。
土壌の通気性を良くすることが根を太らせるポイント。蕪を植える畑は深くしっかりと耕しておきましょう。蕪は小石や固い土の塊などで根別れを起こすので必ず取り除いておきます。
 プランターに入れる用土の量は、鉢の8割にしてウォータースペースを確保します。 プランターに入れる用土の量は、鉢の8割にしてウォータースペースを確保します。
プランターで栽培する時は鉢底石を敷くなどして用土の排水性を良くしておきましょう。排水性が悪いと根腐れ病などの病気が蔓延する原因となります。 |
|
| |
蕪の種蒔き(種の蒔き方)
|
 蕪はポットからの移植が出来ないので、種は畑やプランターに直接蒔いて育てましょう。 蕪はポットからの移植が出来ないので、種は畑やプランターに直接蒔いて育てましょう。
種は種点蒔き・筋蒔き・バラ蒔きが可能です。点蒔きは植える間隔が広いので間引きの手間が楽になる蒔き方です。間引いた苗を料理に使いたい方は筋蒔きがおすすめ。バラ撒きは苗を間引く時や施肥の管理に手間がかかるのであまりおすすめ出来ません。
蕪の種を点蒔きする時は、空き缶やペットボトルの裏側を用土に押し当てて蒔き穴を作ります。そこに4~5粒ほど種を蒔きましょう。
通常のカブは20㎝~25㎝、小カブは10~20㎝植え付けの間隔を取って種を蒔くようにします。
 蕪を筋蒔きする時は条間を10~15㎝取り棒などを使って深さ5~10㎜のまき溝をつけましょう。 蕪を筋蒔きする時は条間を10~15㎝取り棒などを使って深さ5~10㎜のまき溝をつけましょう。
種は5㎜~1㎝間隔で蒔いて種を植えたあとは薄く覆土してやります。この時に用土を被せすぎると発芽率が下がるので注意しましょう。
 蕪の栽培で使う用土は篩などで土の粒を揃えてやると、根が分かれる「また根」になることを防ぐことが出来ます。 蕪の栽培で使う用土は篩などで土の粒を揃えてやると、根が分かれる「また根」になることを防ぐことが出来ます。
蕪の種を蒔いて土を被せた後は手のひらや木の板などで軽く上から押さえましょう。被せた用土を抑えることで水やりの時に種が表面に流れ出るのを防げます。
 種を蒔いた後は芽が出るまで毎日十分に水やりを行いましょう。蕪の発芽は種を植えてから4~5日ほどで始まります。 種を蒔いた後は芽が出るまで毎日十分に水やりを行いましょう。蕪の発芽は種を植えてから4~5日ほどで始まります。
蕪の種は小さいので強く水やりをすると種が表面に流れ出てしまいます。ジョウロのハス口を上向きにして水を与えましょう。
種を蒔いてから発芽するまでの水やりが少ないと、種が発芽しないことがあります。 |
|
| |
蕪の間引きのタイミング
|
 蕪の間引きのタイミングは隣り合う葉と葉が重なり合った時です。 蕪の間引きは根を太らせるために重要な作業となので、適期に行うことが大切です。 蕪の間引きのタイミングは隣り合う葉と葉が重なり合った時です。 蕪の間引きは根を太らせるために重要な作業となので、適期に行うことが大切です。
筋蒔きの間引きのタイミングは全ての発芽が揃った時で、点蒔きの場合は本葉が2~3枚になった時にそれぞれ1回目の間引きを行いましょう。
筋蒔きの間引きは、2~3㎝間隔(本葉どうしが重ならない程度)に間引きます。苗を間引いた後は、苗が倒壊しないよう真っ直ぐに蕪に土寄せをしましょう。
 点蒔きの1回目間引きと筋蒔きの2回目の間引きは、本葉が2~3枚に成長した頃に行いましょう。 点蒔きの1回目間引きと筋蒔きの2回目の間引きは、本葉が2~3枚に成長した頃に行いましょう。
点蒔きは1育ちの良い苗を1か所あたり3本残して他の苗はすべて間引いてしまいます。筋蒔きは葉と葉が重ならない程度に間引いてやります。
苗が密集していて根が絡まりあっている時に、手で強引に抜き取ってしまうと残したい株ごと抜けてしまうことがあります。良い苗を確実に残したい時はハサミなどを使って根元から切り取るようにしましょう。
間引いた後は株もとに土寄せを行っておきます。
 最終の間引きは本葉が5~6枚になった頃で、この時に株間を20~25㎝(小カブは8~10㎝)空けて元気な苗を1本にします。 最終の間引きは本葉が5~6枚になった頃で、この時に株間を20~25㎝(小カブは8~10㎝)空けて元気な苗を1本にします。
この頃は蕪が根付いて成長を始めているので、手で抜けない時はハサミを使って根元から切って間引いてしまいましょう。 |
|
| |
蕪の水やりの頻度と量
|
 蕪は種を撒いて発芽するまでの間は水はりを欠かさないようにしましょう。土の表面が乾いた時にこまめに水やりをします。 蕪は種を撒いて発芽するまでの間は水はりを欠かさないようにしましょう。土の表面が乾いた時にこまめに水やりをします。
芽が出てからは土の表面の乾燥が目立った時に水やりを行いましょう。蕪は多湿を嫌う野菜なので気温が上がる日中に水やりを行います。気温が下がる夕方以降の水やりは病気が発生する要因です。
根の肥大期に入ったら水やりを忘れずに行いましょう。水不足は裂根の原因となります。 |
|
| |
蕪に与える追肥の量と頻度(タイミング)
|
 蕪の追肥は2回目の間引きの後と最後の間引きを行った時です。根を肥大させるためには追肥の量とタイミングがポイントです。 蕪の追肥は2回目の間引きの後と最後の間引きを行った時です。根を肥大させるためには追肥の量とタイミングがポイントです。
2回目の間引きのあと、株元周辺に化成肥料を1株当たり3~5gほど周辺の土に蒔いて混ぜ合わせたものを株もとに寄せておきましょう。
蕪の2回目の追肥は最終の間引きと同じタイミングで与えます。1回目追肥と同様に化成肥料を1株当たり3~5g程度、株もとに撒いて周辺の土と混ぜ合わせて株もとに寄せて与えましょう。
蕪は多肥性の野菜です。根の肥大が始まったら肥料を忘れずに施すのが根を大きく太らせるポイント。与える肥料も窒素分を多く含むものを与えると、根より葉が育ってしまうので注意しましょう。
根の生育が急速になる時期ほど肥料の吸収力は活発になり、この時期に肥料切れになると根が小さい味が悪い蕪になってしまうので注意が必要です。 |
|
| |
蕪の収穫適期(タイミング)
|
 蕪が収穫出来るようになる日数は、種を蒔いてから大カブで60~100日小カブで40~50日程度です。収穫時期は育てる品種によって違うので注意しましょう。 蕪が収穫出来るようになる日数は、種を蒔いてから大カブで60~100日小カブで40~50日程度です。収穫時期は育てる品種によって違うので注意しましょう。
収穫適期を見た目で収穫時期を判断する時は、根の直径が10㎝(子カブは5~6㎝)になったものを選びましょう。
 蕪を収穫する時は大きく育っている株から順番に葉の付け根の部分を掴んで手で引き抜いて豪快に収穫します。収穫しましょう。 蕪を収穫する時は大きく育っている株から順番に葉の付け根の部分を掴んで手で引き抜いて豪快に収穫します。収穫しましょう。
残した小さな蕪は更に肥大させるために、引き抜いた収穫後の穴を忘れずに埋めておくようにします。
蕪は収穫の時期を逃すと「ス」が入ってしまいます。「す」が入ると中がスカスカになり、味と食感が落ちるので収穫のタイミングを逃さないようにしましょう。
ス入りかどうかは、外葉を千切って葉柄の断面に空洞が出来ているかどうかで簡単に判断できます。 |
|
| |
| |
| |
| |
カブ栽培のまとめと病気対策・害虫駆除
|
 蕪を上手に育てるポイントは追肥と間引きです。間引きの適期を守り追肥の種類や量・与える時期が重要になります。 蕪を上手に育てるポイントは追肥と間引きです。間引きの適期を守り追肥の種類や量・与える時期が重要になります。
有機質を多く富んだ通気性と排水性と保水性を兼ね備えた用土で育てると蕪は根が大きなって丈夫に育てられます。
土の中に障害物(石・木の根・土の塊)や、未熟な有機物(未収穫の根野菜)があると根が分かれる原因となるのでしっかりと取り除いてから種を蒔くようにしましょう。
 蕪を育てる時に発生する病気には、白さび病をはじめ、黒腐れ病・根こぶ病・萎黄病などがあります。 蕪を育てる時に発生する病気には、白さび病をはじめ、黒腐れ病・根こぶ病・萎黄病などがあります。
病気が発生する最大の原因は多湿環境です。プランター栽培では鉢底石を敷く露地栽培では高畝栽培するなど工夫しましょう。
 カブによく発生する害虫は、カブラハバチ・キスジノミハムシ・アオムシ・アブラムシなどで、葉を食害する害虫が多いのが特徴です。 カブによく発生する害虫は、カブラハバチ・キスジノミハムシ・アオムシ・アブラムシなどで、葉を食害する害虫が多いのが特徴です。
実は土中に潜り根を食い荒らす虫がいます。その害虫はキスジノミハムシ。幼虫が根の部分に食害痕を残すうえ、発見が収穫までわからないのでやっかいな害虫です。
害虫が少数の時は手で捕獲出来ますが、多発した時は早期の使用であれば人体への害も少ないので、散布剤等の使用も検討してみましょう。害虫は早期駆除が有効です。
成虫の飛来や食害跡を見つけたら、葉の裏などを良く観察して早期発見を心掛けましょう。
 蕪の幼苗期に害虫を発生させてしまうと一晩で被害が大きくなることもあるので注意が必要です。 蕪の幼苗期に害虫を発生させてしまうと一晩で被害が大きくなることもあるので注意が必要です。
寒冷紗をかけて栽培すれば、成虫の飛来を大幅に防ぐことが出来ます。 |
|
| |
| |
| |
|
野菜の育て方(根菜類一覧)
|
|
簡単!野菜の育て方のトップページ
|
| |
蕪の育てやすい品種は?
|
 蕪は大きく分けるとヨーロッパ型とアジア型の2種類。日本各地では品種改良された域特産の様々な種類のカブが販売されています。 蕪は大きく分けるとヨーロッパ型とアジア型の2種類。日本各地では品種改良された域特産の様々な種類のカブが販売されています。
蕪の見た目はどれも似ていていますが、味と食感は品種によって様々です。サラダや漬物用の食感が柔らかいものや煮物や味噌汁に使う風味の良い品種など、使い方に合わせて選びましょう。
初心者でも比較的育てやすい蕪の品種は、金町系の「しらたま」「たかね」「はくれい」「はくたか」と言われています。
早取りが可能で変形やス入りが少ないのは「福小町」、病害虫に強く根の太りが良い「玉里」、赤色をした「愛真紅」、根の上半分だけ赤くなる「あやめ雪」、細長い形をした蕪「日野菜蕪」などが人気です。
どの品種でも簡単に育つので、自分の好みの品種を育ててみましょう。プランターで栽培する時は小カブと言われるミニ種は収穫までが短くて育てやすくおすすめです。 |
|
|
楽天市場で人気の種はこちら(クリック)
amazon「蕪」の種はこちら(クリック)
|
|
| |
| |
| |
| |
copyright© 簡単!野菜の育て方
all rights reserved. |
| 運営者情報 |
|